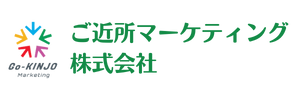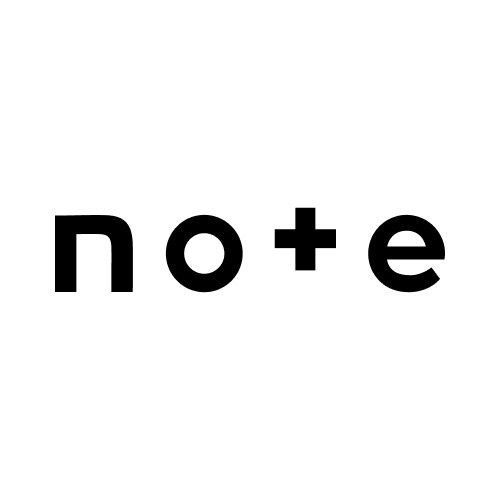泉のマーケティング解説ブログ
2025.05.13
最寄り商圏の設定について
商圏の設定の事例
最寄り商圏の設定は候補地選定時の一つの目安であり、開店後の日々のお店の営業で広くも狭くもなることを示す事例です。
事例 別荘地でのコンビニ出店

背 景
別荘地の概要は半径約1km、世帯数約1,000世帯、人口1,800人(うち65歳以上が65%)で、外部からの出入りはほとんどない。
位 置
店舗は別荘地の入口に位置し、店舗中心なら端の住居まで2km。
既存店の状況
以前の売店の1日の来店客は100人以下、日によっては50人まで落ち込んでいた。
通常のコンビニ切り替え効果
年商は通常3倍程度だが、このケースでは4倍以上。
成功の鍵
-
1.商圏設定の認識共有
-
- 別荘地では住民の多くが車を利用しており、敷地内のほとんどの場所から5分で来店可能
- コンビニの通常の商圏設定350mを超え、2kmの商圏設定をお店と共有
-
2.販促活動
-
-
開店前に従業員による商品説明会を6回開催。
-
従業員が商品を理解し、高齢者中心に商品(牛乳、卵、食パン、納豆、チルド総菜等)の品質を試食会で確認。
-
-
3.現地確認と調査の活用
-
-
オーナーが商圏をくまなく回り、住民の暮らしぶりを把握。
-
品揃えを住民のニーズに合わせて調整。
-
結果
|
来店客の増加
|
1日に400人以上が利用するお店に成長。 |
|---|---|
|
固定客の確保
|
住民が固定客となり、コミュニケーションを大切にし、ニーズに応じた品揃えの変更を実施。 |
|
継続的な売上
|
5年経過しても売上は落ちず、別荘地の住民にとって欠かせない存在に。 |
この事例から学ぶことは、商圏設定の重要性と、住民のニーズをしっかり把握し、それに応じたサービスを提供することで、商圏の広さや顧客数を最大限に活用できるということです。
まとめ
最寄り商圏は出店候補地の一つの目安であり、実際の営業活動により拡張も可能です。
商圏設定の重要性と、住民のニーズをしっかり把握し、相応しいサービスの提供により、店舗経営に役立てます。