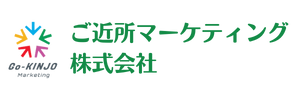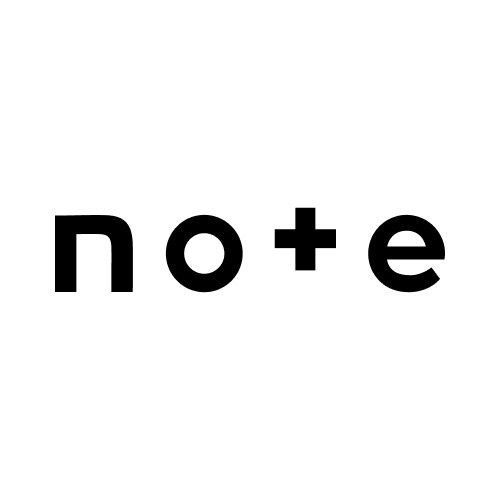泉のマーケティング解説ブログ
2025.08.11
これからのコンビニは「個店の戦略」が鍵になる
近年、スーパー各社が中規模店にシフトし、惣菜や店内調理で力をつける中、コンビニ各社の苦戦が目立つようになってきました。
特に「価格が高い」「おにぎりや弁当が魅力を失った」という声が消費者の中でも多く聞かれます。
これは、店内調理のスーパーと、工場チルド配送のコンビニの構造的な違いが露呈している結果です。
これは、店内調理のスーパーと、工場チルド配送のコンビニの構造的な違いが露呈している結果です。
では、コンビニはこのまま沈んでいくしかないのでしょうか?
いいえ、生き残る道は、確実にあります。
その鍵は、“誰に・何を・どこで届けるか”というマーケティングの原点に立ち返ること。
そして、現場の一店舗一店舗が主役になることです。
コンビニは「一番近い便利」の再定義から始めよ
スーパーは「家族のために買いに行く場所」。一方コンビニは「自分のために買う場所」とされてきました。
でも、その使われ方は本当に固定されたものではありません。
例えば、半径350m圏内の住民が「普段使い」に変われば、コンビニの立ち位置も変わるのです。
その証拠が、富士市三ッ倉店の事例です。
ご近所マーケティングの成果(富士市三ッ倉店)
|
商圏人口
|
350m圏内、約250世帯
|
|
施策
|
廃棄を出さない商品の告知・告知エリアの最適化
|
|
結果
|
2024年1年間で 3,650人 の客数増
|
2025年も引き続き、1日平均 30人増 を維持中
この結果は偶然ではありません。
商圏を分析し、「近くにいるが来ていない人」に向けて戦略的にアプローチしたことで生まれた成果です。
本部主導ではなく“個店の戦略”が活きる時代へ

この取り組みには、本部の全国一律戦略ではなく、店主の主体性が不可欠です。
一見難しく思えるかもしれませんが、セブン-イレブンには他チェーンにない強みがあります。
それは、オーナーに主体性がある文化が残っていることです。
だからこそ、全店でなくてもいい。1店からでも取り組める。
それが、他チェーンとの差別化になり、これからの「強い店」になっていきます。
個店の時代 問われるのは“半径350mの顧客への解像度”

商圏分析はセブン-イレブンが出店時に徹底して行ってきた手法です。
でも、それを運営に活かしている店舗はほとんどありません。
お店の5分圏内には、まだ来ていない人がたくさんいます。
そこに対し、「あなたのための便利」を届けるための戦略が、ご近所マーケティングです。
まとめ
本部の仕組みに頼る時代は終わりました。
これからの主役は、現場で“考えて動く店”です。
ご近所マーケティングは、
地域に生きるお店が、自分の力で繁盛を作っていくための仕組みです。
1店舗ずつ、日本の商売に元氣を取り戻していきましょう。