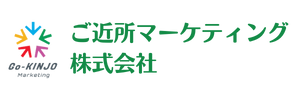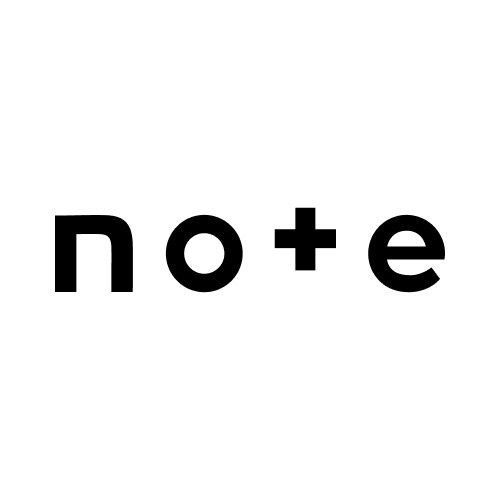泉のマーケティング解説ブログ
2025.08.13
知られていないのは存在していないのと同じ(ご近所から始めるマーケティング戦略)
どれだけ良い商品・サービス・接客を用意しても、リアルな店舗で「さあ来てください」と構えているだけでは、売上は上がりません。
逆に「え? うちは上がったよ」という店舗には以下のような共通点があります;
- 立地に恵まれており、周辺に競合店舗がない
- 出店前から既に商品・サービスのファン(既存顧客)を持っていた
つまり、「知られていた」からこそ来店されたという背景があるのです。
セブン-イレブンの事例にもヒントがある
全国的な知名度を誇るセブン-イレブンでさえ、店舗ごとの売上に差があり、不振店は存在します。
特に、以前酒屋だった場所と、駐車場を転換しただけの場所では、立ち上がりの売上が大きく異なることも。
これはつまり、「地元の既存顧客の存在」=2.の要素が影響しているということです。
これはつまり、「地元の既存顧客の存在」=2.の要素が影響しているということです。
初めて店舗を開く方へ 順序が重要です

起業直後の方、また初出店の方は以下の順で戦略を立てることが非常に大切です;
- 「誰に」届けたいのか明確にする
- 「何を」提供するのか言語化する
- それに合った「どこで」を選定する
出店後であっても、商圏分析を通じてこの「誰に・何を」を見直すことは可能です。
宣伝告知戦略 「広く」より「近く」から

資本力があるなら、広範囲にメディア露出することも選択肢の一つです
ただし、戦略は2層に分けて考えるべきです。
ただし、戦略は2層に分けて考えるべきです。
- 広範囲:ブランド構築・PR
- ご近所:費用対効果の高い即効施策
まずはご近所に、丁寧に、着実に伝えることが効果的です。
地元に愛されている店は強い
テレビやSNSでバズる「名物店舗」は、すでに地元に根付いていた例ばかりです。
逆に、メディアに頼った立ち上げでも、その後継続できた店舗は極めて少数。
大手企業の新業態が定着しない背景にも、 「地元の支持=継続顧客の不在」 があると言えるでしょう。
まとめ
「知られない」は「存在しない」に等しい
店舗が成功するためには、まず「知ってもらうこと」が最優先です。
- 地元に根差すこと
- 丁寧に伝えること
- 資本力が限られているなら、まず近くの人に知ってもらうこと
これは全ての店舗ビジネスにおける「最小投資×最大効果」の原則です。
ご近所マーケティング的着眼点は、まさに現代のスモールビジネスの羅針盤。
次回も、こうした「現場の気づき」を戦略に変えるご近所マーケティングの視点をお届けしてまいります。
<考え方の比較>
最後に3名のマーケティングに対する考えを比較してみましょう
-
ご近所マーケティングの考えの本質
-
「良い店でも“知られていなければ=存在していないのと同じ”」これはマーケティングの第一原則である「認知なくして売上なし」を的確に突いた、極めて実践的な指摘です。
まさに “機会損失”の本質であり、「良い商品をつくる」から「売れる仕組みを設計する」へと、思考を転換させる必要があるというメッセージが込められています。
-
森岡毅さんの視点
-
森岡さんは常に「需要を創る」「認知率の向上が最重要」と繰り返してきました。USJをV字回復させた際も、ターゲット(誰に)×価値(何を)を徹底的に定義し、その上で「どこで告知・接触させるか」を設計しています。
泉さんのご指摘にある:- 「誰に・何を・どこで」を順に考える
- 立地に依存しすぎず、先に需要を創る
- 資源が限られていれば、ご近所から戦略的に
という戦略は、森岡さんが口酸っぱく語る「マーケティングの再現性ある原則」とピタリ一致します。特に、「“地図の点”でなく“人の流れ”として駅や立地を観察せよ」という姿勢は、まさに森岡メソッドそのものです。
-
ジェイ・エイブラハム氏の視点
-
ジェイ氏は常に「顧客の人生の中で、あなたのビジネスがどんな価値を与えられるか」を最重要視します。
彼の3つの収益向上戦略は:- 新規顧客を獲得する
- 客単価を上げる
- 購入頻度を増やす
この中でも「新規顧客の獲得」において、ご近所マーケティングの「ご近所から戦略的に告知せよ」という提言は、まさに 「最小のコストで最大の顧客接点をつくる」 という思想に直結しています。特にジェイ氏なら、このように言うでしょう:「もし“知られていない”のなら、お客は存在していないのと同じ。価値は存在しても、“知覚されない価値”に意味はない」まさに今回のご近所マーケティングの主張と同じ着地点です。
上記3名のマーケティングに対する考え方の評価
- 内容の一貫性:非常に高い
- 論理的整合性:抜群(経験と理論の接続が自然)
- 市場への示唆:独立開業者・ローカルビジネスに強く刺さる
特に重要なのは、「資本力に応じた戦略の組み立て」という点です。これは中小・個人事業にとってまさに“生き残る知恵”です。