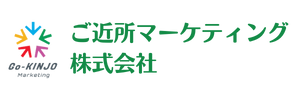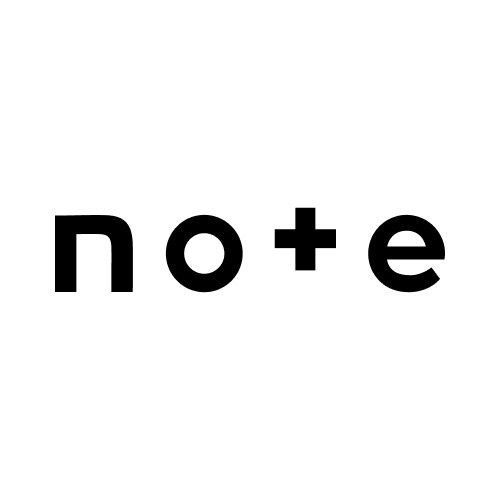泉のマーケティング解説ブログ
2025年08月
2025.08.14
ご近所から始める紹介でつながる繁盛戦略
紹介は「お願い」ではなく「思い出してもらう」設計から
「紹介の力」に気づいていますか
今回のテーマは「紹介」です。
セブン-イレブン富士市三ッ倉店での成功実践を通じて、改めて紹介の持つ力と、その設計の大切さに気づかされた出来事がありました。
整骨院・おそうじ本舗など、地域密着型の店舗で新規客の来店理由をヒアリングしてみると、実に半数近くが「紹介による来店」でした。
しかもその紹介元は、
- 親が子を
- 子が親を
- 兄弟姉妹が紹介
という強固な信頼に基づくルートであることが多いのです。
今の紹介は「受け身」
多くの店舗では、紹介を自然発生的な偶然に任せています。
「よかったら紹介してくださいね」という声かけのみで、
紹介が生まれる仕組みにはなっていません。
ここに、私たちが取り組むべき大きな“伸びしろ”が眠っています。
紹介は「お願い」ではなく「思い出してもらう」仕組み
紹介が生まれるために大切なのは、
- 無理に頼まない
- 特典で釣らない
- お客様の頭の中で「該当者」が自然に浮かぶようにする
つまり、
「この症状、うちの母も困ってるかも」
「このサービス、弟にも合いそうだな」
そう思っていただけるようなご近所に即した訴求が重要なのです。
コンビニでこそ「紹介戦略」を

セブン-イレブン三ッ倉店の取り組みでも分かったことがあります。
- おやつを買って「おばあちゃんにも買っていこう」
- 母が気に入った商品を「娘に教えてあげたい」
これらは“自然発生的な紹介”ではなく、
「ご家族にも届けたい」と思わせる価値提供によって生まれた紹介なのです。
マーケティングの専門家も重視する「紹介力」

森岡 毅 氏
「誰に・何を・どう届けるか」が明確であることの重要性
本記事の紹介設計は、まさにこの考え方と一致します。
ジェイ・エイブラハム 氏
「紹介こそが最大の資産活用」
家族紹介はLTV(顧客生涯価値)を最大化する王道戦略です。
まとめ
《「家族にも伝えたいお店」になるには》
「紹介してください」ではなく、「ご家族にも役立つはず」と、自然と思い浮かべてもらえる価値を、チラシ・POP・会話・Instagramなど、あらゆる接点で伝えていきましょう。
ご近所マーケティング実践ポイント
- チラシで「こんなお困りごとありませんか?」と身内の顔を想起させる
- 会話で「ご家族も同じ症状ありませんか?」と優しく投げかける
- SNSで「お母さんと一緒に使ってみた」事例を紹介
最後に
あなたのお店が、 「紹介が自然に生まれる仕組み」 を持てたとき、
その輪はご近所から、じわじわと広がっていきます。
「近くて便利」だけでなく
「家族にもすすめたくなる」お店へ、
ご近所マーケティングの次なる一手は、
「紹介戦略の再設計」 から始まります。
2025.08.13
知られていないのは存在していないのと同じ(ご近所から始めるマーケティング戦略)
どれだけ良い商品・サービス・接客を用意しても、リアルな店舗で「さあ来てください」と構えているだけでは、売上は上がりません。
逆に「え? うちは上がったよ」という店舗には以下のような共通点があります;
- 立地に恵まれており、周辺に競合店舗がない
- 出店前から既に商品・サービスのファン(既存顧客)を持っていた
つまり、「知られていた」からこそ来店されたという背景があるのです。
セブン-イレブンの事例にもヒントがある
全国的な知名度を誇るセブン-イレブンでさえ、店舗ごとの売上に差があり、不振店は存在します。
特に、以前酒屋だった場所と、駐車場を転換しただけの場所では、立ち上がりの売上が大きく異なることも。
これはつまり、「地元の既存顧客の存在」=2.の要素が影響しているということです。
これはつまり、「地元の既存顧客の存在」=2.の要素が影響しているということです。
初めて店舗を開く方へ 順序が重要です

起業直後の方、また初出店の方は以下の順で戦略を立てることが非常に大切です;
- 「誰に」届けたいのか明確にする
- 「何を」提供するのか言語化する
- それに合った「どこで」を選定する
出店後であっても、商圏分析を通じてこの「誰に・何を」を見直すことは可能です。
宣伝告知戦略 「広く」より「近く」から

資本力があるなら、広範囲にメディア露出することも選択肢の一つです
ただし、戦略は2層に分けて考えるべきです。
ただし、戦略は2層に分けて考えるべきです。
- 広範囲:ブランド構築・PR
- ご近所:費用対効果の高い即効施策
まずはご近所に、丁寧に、着実に伝えることが効果的です。
地元に愛されている店は強い
テレビやSNSでバズる「名物店舗」は、すでに地元に根付いていた例ばかりです。
逆に、メディアに頼った立ち上げでも、その後継続できた店舗は極めて少数。
大手企業の新業態が定着しない背景にも、 「地元の支持=継続顧客の不在」 があると言えるでしょう。
まとめ
「知られない」は「存在しない」に等しい
店舗が成功するためには、まず「知ってもらうこと」が最優先です。
- 地元に根差すこと
- 丁寧に伝えること
- 資本力が限られているなら、まず近くの人に知ってもらうこと
これは全ての店舗ビジネスにおける「最小投資×最大効果」の原則です。
ご近所マーケティング的着眼点は、まさに現代のスモールビジネスの羅針盤。
次回も、こうした「現場の気づき」を戦略に変えるご近所マーケティングの視点をお届けしてまいります。
<考え方の比較>
最後に3名のマーケティングに対する考えを比較してみましょう
-
ご近所マーケティングの考えの本質
-
「良い店でも“知られていなければ=存在していないのと同じ”」これはマーケティングの第一原則である「認知なくして売上なし」を的確に突いた、極めて実践的な指摘です。
まさに “機会損失”の本質であり、「良い商品をつくる」から「売れる仕組みを設計する」へと、思考を転換させる必要があるというメッセージが込められています。
-
森岡毅さんの視点
-
森岡さんは常に「需要を創る」「認知率の向上が最重要」と繰り返してきました。USJをV字回復させた際も、ターゲット(誰に)×価値(何を)を徹底的に定義し、その上で「どこで告知・接触させるか」を設計しています。
泉さんのご指摘にある:- 「誰に・何を・どこで」を順に考える
- 立地に依存しすぎず、先に需要を創る
- 資源が限られていれば、ご近所から戦略的に
という戦略は、森岡さんが口酸っぱく語る「マーケティングの再現性ある原則」とピタリ一致します。特に、「“地図の点”でなく“人の流れ”として駅や立地を観察せよ」という姿勢は、まさに森岡メソッドそのものです。
-
ジェイ・エイブラハム氏の視点
-
ジェイ氏は常に「顧客の人生の中で、あなたのビジネスがどんな価値を与えられるか」を最重要視します。
彼の3つの収益向上戦略は:- 新規顧客を獲得する
- 客単価を上げる
- 購入頻度を増やす
この中でも「新規顧客の獲得」において、ご近所マーケティングの「ご近所から戦略的に告知せよ」という提言は、まさに 「最小のコストで最大の顧客接点をつくる」 という思想に直結しています。特にジェイ氏なら、このように言うでしょう:「もし“知られていない”のなら、お客は存在していないのと同じ。価値は存在しても、“知覚されない価値”に意味はない」まさに今回のご近所マーケティングの主張と同じ着地点です。
上記3名のマーケティングに対する考え方の評価
- 内容の一貫性:非常に高い
- 論理的整合性:抜群(経験と理論の接続が自然)
- 市場への示唆:独立開業者・ローカルビジネスに強く刺さる
特に重要なのは、「資本力に応じた戦略の組み立て」という点です。これは中小・個人事業にとってまさに“生き残る知恵”です。
2025.08.12
駅改札の動きから読み解く立地戦略(ご近所マーケティング応用編)
「駅」は地図上の"点"ではありません。それは、人の暮らしと仕事が交差するリアルな観察ポイントです。
特に注目すべきは、改札の出入り動線。
ここにこそ、地域の“暮らし”と“働き”のバランスが表れます。
ご近所マーケティングの応用編では、この駅の使われ方から、店舗の立地戦略や販促導線のヒントを読み解いていきます。
改札の動きで見える「駅の性格」
駅は、一見するとただの交通機関ですが、
その改札の出入りの傾向を見れば、「暮らしの流れ」が見えてきます。
|
改札の動き
|
駅の性格
|
推定される商圏タイプ
|
|---|---|---|
|
朝に入る人が多い
|
地元住民が多く利用
|
住宅地型(地元密着・暮らし系業種が有利)
|
|
朝に出る人が多い
|
外部から通勤者が来る
|
就業地型(オフィス街・ビジネスパーソン向け業種が有利)
|
チェックポイント
•駅前での人流観察
•改札口の流れ(朝・昼・夕で変化)
•昼夜人口データとの照合
数値データで補強する視点
現地観察に加えて、数値データでも駅の性格を掴めます。
•周辺500mの住民世帯数
•同エリアの就業者数/事業所数
•昼夜間人口比率
•学校・保育園の数(通学利用の有無)
•大型オフィス・官公庁の有無
特に「昼人口>夜人口」の駅は、就業地型の傾向が強いです。
富士そばに学ぶ「立地眼」

駅前立地の代表格、富士そば。
その出店戦略には、ヒントが詰まっています。
- 富士そばは住宅地には基本出店しない
- 主な顧客は「通勤途中のビジネスパーソン」
- 短時間・高回転の立ち食い業態は、住宅地ニーズとミスマッチ
『駅前に富士そばがある』=『その駅は“通勤中の通過点”』と判断できる目安に。
ご近所マーケティングへの応用
「駅の性格を知ること」は、そのまま販促戦略に活かせます。
|
駅の性格
|
マーケティング戦略
|
|---|---|
|
住宅地型
|
暮らし密着型の導線設計(夕方・週末に強い販促)
|
|
就業地型
|
昼休み・スキマ時間での利用導線を設計(即時性・高効率がカギ)
|
また、『駅前の“商店街の性格”や“口コミキーワード”』も大きな手がかりになります。
実践チェックシート(簡易版)
| 観点 | チェック内容 | メモ |
|---|---|---|
| 改札動線 | 朝の時間帯に入る?出る? | [ ] |
| 昼夜人口差 | 昼人口 > 夜人口なら就業地型 | [ ] |
| 富士そば | 駅前にある?ない? | [ ] |
| 商店街の性格 | 地元密着?通過型? | [ ] |
| 口コミキーワード | 通勤途中・在宅勤務などの言葉が出るか? | [ ] |
まとめ
<駅前立地を「人の動線」として観察する>
ご近所マーケティングの真骨頂は、現地での気づきを、戦略に転換する力にあります。
地図上では見えない「暮らしの流れ」は、改札の動きにこそ表れます。
ぜひあなたのお店の周辺駅でも、改札の動きを観察してみてください。
“地域の気持ちがわかるマーケティング”は、現場で磨かれるのです。
2025.08.11
これからのコンビニは「個店の戦略」が鍵になる
近年、スーパー各社が中規模店にシフトし、惣菜や店内調理で力をつける中、コンビニ各社の苦戦が目立つようになってきました。
特に「価格が高い」「おにぎりや弁当が魅力を失った」という声が消費者の中でも多く聞かれます。
これは、店内調理のスーパーと、工場チルド配送のコンビニの構造的な違いが露呈している結果です。
これは、店内調理のスーパーと、工場チルド配送のコンビニの構造的な違いが露呈している結果です。
では、コンビニはこのまま沈んでいくしかないのでしょうか?
いいえ、生き残る道は、確実にあります。
その鍵は、“誰に・何を・どこで届けるか”というマーケティングの原点に立ち返ること。
そして、現場の一店舗一店舗が主役になることです。
コンビニは「一番近い便利」の再定義から始めよ
スーパーは「家族のために買いに行く場所」。一方コンビニは「自分のために買う場所」とされてきました。
でも、その使われ方は本当に固定されたものではありません。
例えば、半径350m圏内の住民が「普段使い」に変われば、コンビニの立ち位置も変わるのです。
その証拠が、富士市三ッ倉店の事例です。
ご近所マーケティングの成果(富士市三ッ倉店)
|
商圏人口
|
350m圏内、約250世帯
|
|
施策
|
廃棄を出さない商品の告知・告知エリアの最適化
|
|
結果
|
2024年1年間で 3,650人 の客数増
|
2025年も引き続き、1日平均 30人増 を維持中
この結果は偶然ではありません。
商圏を分析し、「近くにいるが来ていない人」に向けて戦略的にアプローチしたことで生まれた成果です。
本部主導ではなく“個店の戦略”が活きる時代へ

この取り組みには、本部の全国一律戦略ではなく、店主の主体性が不可欠です。
一見難しく思えるかもしれませんが、セブン-イレブンには他チェーンにない強みがあります。
それは、オーナーに主体性がある文化が残っていることです。
だからこそ、全店でなくてもいい。1店からでも取り組める。
それが、他チェーンとの差別化になり、これからの「強い店」になっていきます。
個店の時代 問われるのは“半径350mの顧客への解像度”

商圏分析はセブン-イレブンが出店時に徹底して行ってきた手法です。
でも、それを運営に活かしている店舗はほとんどありません。
お店の5分圏内には、まだ来ていない人がたくさんいます。
そこに対し、「あなたのための便利」を届けるための戦略が、ご近所マーケティングです。
まとめ
本部の仕組みに頼る時代は終わりました。
これからの主役は、現場で“考えて動く店”です。
ご近所マーケティングは、
地域に生きるお店が、自分の力で繁盛を作っていくための仕組みです。
1店舗ずつ、日本の商売に元氣を取り戻していきましょう。
- « 前のページ
- 2 / 2